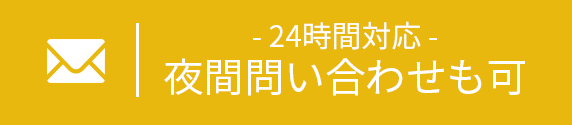コラム
後遺障害の逸失利益とは?わかりやすく計算方法を解説!
2025.05.13 後遺症交通事故で後遺障害が残ると、認定された等級や将来の収入の減少に対して「逸失利益」が認められるケースがあります。
逸失利益は慰謝料とは異なる損害で、その計算は複雑です。
この記事では、逸失利益とは?から計算方法などを弁護士がわかりやすく解説します。
適正な賠償額を受け取るためには弁護士をうまく活用しましょう。
交通事故の後遺症で仕事に支障が出てしまうと、将来の収入が心配になるものです。
後遺症のために思うように体を動かせないことが原因で、今までできていた業務ができなかったり、昇進のチャンスを逃したりするケースは珍しくありません。
後遺障害が認められると「逸失利益」という損害賠償が発生します。
しかし、その内容や計算方法がわからず、十分な補償が受けられないのではと不安になる方は多いです。
本記事は、後遺障害逸失利益に関して具体的な計算方法などを弁護士が詳しく解説します。
逸失利益の仕組みを理解することで、適正な補償を受ける第一歩になります。
後遺障害逸失利益とは?
後遺障害逸失利益は事故により後遺症が残り、将来得られるはずだった収入が減ることによって生じる経済的損失をいいます。
交通事故などで後遺障害が認定されると、働く力が一部または全部失われることになります。
このような場合、将来にわたる収入の減少分の賠償を加害者へ請求可能です。
以前と同じように働けなくなった人にとって、逸失利益の補償は大切な生活の支えです。
具体的な計算については、後述します。
ここでは逸失利益と間違えられやすい休業損害や慰謝料との違いについても触れておきます。
休業損害との違い
休業損害は、事故により一時的に働けなくなった期間の収入減を補うものです。
治療や入院中の欠勤が対象です。
後遺障害逸失利益と比較すると、休業損害は一時的な損害賠償といえるでしょう。
一方で、逸失利益は長期的な収入減に対応しています。
対象となる期間や計算方法が異なり、休業損害は日額で算出されるのに対して、逸失利益は将来の収入を年単位で見積もります。
慰謝料との違い
慰謝料との違いは、損害の性質にあります。
慰謝料は事故によって受けた精神的な苦痛を金銭に置き換えて支払われるものです。
そのため、慰謝料は収入に関係なく、後遺障害の等級から金額が決まります。
対して逸失利益は、職業や収入、労働能力喪失率などをもとに個別に計算されるものです。
精神的苦痛への補償か、経済的損失への補償かという点で明確に異なっています。
後遺障害逸失利益の計算方法
逸失利益の計算は事故で働けなくなった分の収入を金銭的に評価するものです。
具体的には、事故前の年収に対して労働能力喪失率と喪失期間に応じたライプニッツ係数を掛けて算出します。
計算に用いられるのは「基礎収入」「労働能力喪失率」「労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数」の3つです。
【後遺障害逸失利益の計算式】
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
それぞれ解説します。
基礎収入
基礎収入は、後遺障害による逸失利益を求める際の出発点となる収入です。
一般的には、事故の前年に得た収入をもとに決定されます。
具体的には、源泉徴収票や確定申告書、給与明細などが基礎収入を割り出す根拠です。
職業や年齢、性別によっては、厚生労働省が公表している賃金センサスという統計資料を使って基礎収入を出すこともあります。
これは、日本人の平均賃金を年齢や性別ごとにまとめたもので、実際の収入が不安定な場合や、収入が平均値より極端に低い場合に適応されます。
たとえば、令和6年の女性全年齢平均は4,194,400円で、1日あたりに換算すると、約11,492円です。
以下は、属性ごとの基礎収入の算出方法をかんたんにまとめた表です。
| 属性 | 基礎収入の算出方法 |
| 会社員 | 事故前年の実収入(手当・賞与含む)をもとに計算 |
| 自営業者 | 申告所得に基づいて判断、低すぎる場合は賃金センサス参照もあり |
| 主婦(主夫) | 賃金センサスの女性全年齢平均、または実収入の高い方を使用(兼業主婦の場合) |
| 子ども・学生 | 賃金センサスの平均賃金を用いる。大学進学が確実なら大卒平均を基礎とすることもある |
| 高齢者 | 家事従事者や再就職の予定があるならば基礎収入が認められることもある |
会社員であれば、基本的には毎月の収入に手当や賞与を含めた金額が基礎収入です。
自営業者は、確定申告書の所得から判断しますが、利益の過小申告や赤字などがある場合は賃金センサスを参照することがあります。
主婦の場合は、家事労働にも価値があるとされ、賃金センサスのデータが使われます。
学生や子どもも同様に、将来の収入を見積もるため賃金センサスの平均が基礎です。
高齢者については、家事労働の有無や就労の見込みなどを考慮して判断されます。
労働能力喪失率
労働能力喪失率は、後遺障害が原因でどれだけ働く力が失われたかを数字で示したものです。
この数値は後遺障害の等級に応じて決まります。
等級が重いほど喪失率は高くなり、逸失利益も大きくなります。
喪失率が何%かによって、将来失う収入の金額が左右されるという考えに基づくものです。
実際の裁判や示談交渉では、医学的な資料や就労実態などをふまえて認定されます。
数字だけで決められるものではなく、個別事情も加味されますが、等級別の目安を下記の表にまとめました。
| 等級 | 労働能力喪失率の目安 |
|---|---|
| 1級 | 100% |
| 2級 | 100% |
| 3級 | 100% |
| 4級 | 92% |
| 5級 | 79% |
| 6級 | 67% |
| 7級 | 56% |
| 8級 | 45% |
| 9級 | 35% |
| 10級 | 27% |
| 11級 | 20% |
| 12級 | 14% |
| 13級 | 9% |
| 14級 | 5% |
労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
労働能力喪失期間は、後遺障害が原因で将来的に働けない期間のことです。
この期間をどう考えるかで逸失利益の金額が大きく変わります。
基本は67歳までの年数をもとに計算をします。
たとえば、30歳の会社員であれば、67-30=37 となり、37年が労働能力喪失期間ということです。
小学生など子どもであれば、18歳で就職したと仮定され、67-18=49 で労働能力喪失期間は49年という考えになります。
また、逸失利益の算定は将来の損害を現在価値に引き直す必要もあります。
これに使われるのが「ライプニッツ係数」です。
ライプニッツ係数を用いることで、将来にわたり毎年失われる収入を一括で現在の金額に換算します。
具体的には、将来発生する損害賠償をまとめて前もって受け取る際に、そのなかに含まれる利息分を差し引いて計算するというものです。
逸失利益は、本来であれば長期間にわたり少しずつ得られる収入が失われたことへの補填ですが、これが一括で支払われると、本来得るはずだった利息以上の金額が払われることになりかねません。
過剰な補償とならないよう、将来的に得られるはずだった利息を控除して損害額を算出するのです。
喪失期間が長くなるほど、係数の値は大きくなります。
年齢や働ける年数によって変わり、同じ収入でも受け取れる金額に違いが出ます。
下記の表は20歳〜50歳を例に係数の目安を示すものです。
| 年齢 | 労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数(年利3%) |
|---|---|---|
| 20歳 | 47年 | 25.025 |
| 30歳 | 37年 | 22.167 |
| 40歳 | 27年 | 18.327 |
| 50歳 | 17年 | 13.166 |
係数は年利3%で計算した標準的な数値に基づいています。
実際の裁判・示談においては、個別事情や中間利率の変更により異なる場合があります。
あくまで一般的な目安であり、実際の損害賠償請求にあたっては、弁護士などの専門家による個別の検討が不可欠なので注意しましょう。
後遺障害逸失利益に関するよくある疑問
後遺障害逸失利益はその計算が非常に複雑かつ、ケースバイケースの計算が求められるとわかりました。
とくに後遺障害逸失利益を考える際によく耳にする質問は次の2つです。
- ・交通事故にあったのが休職中だった場合
- ・後遺障害が原因で収入が減っていない場合
それぞれについて回答します。
交通事故にあったのが休職中だった場合
事故当時に休職中だった場合でも、後遺障害逸失利益がまったく認められないとは限りません。
判断のカギとなるのは「働く意思と能力があったかどうか」です。
たとえば、復職予定があった場合や、求職活動を行っていた事実があれば、逸失利益を請求できる可能性があります。
実際に職場復帰が決まっていた、もしくは就職活動をしていた際の被害だったと証明できれば、収入がなかったとしても「就労の見込みがあった」と評価されることがあります。
ただし、その証明には、内定通知書や職務経歴、就職活動の記録などの資料が必要です。
収入のない期間でも将来的な労働能力に支障が出たことを根拠に請求できるケースもあるため、状況に応じた対応が必要でしょう。
判断が難しい場合は、弁護士などの専門家への相談が有効です。
後遺障害が原因で収入が減っていない場合
事故後に収入が下がっていないと、原則後遺障害逸失利益は認められません。
ただし、例外も存在します。
たとえば、職場の厚意により仕事内容が軽くなったり、特別な配慮によって勤務を続けていたりする場合などです。
また、自分の努力で同じ収入を維持しているケースでも、後遺障害が仕事に支障を及ぼしていれば考慮されることがあります。
昇進の機会が減る、将来の退職リスクが高まるなど、今は収入が変わっていなくても将来的な影響が見込まれる場合も同様です。
とくに、後遺障害14級のように労働能力喪失率が小さい等級では、減収は表面化しにくいですが、逸失利益が否定されるとは限りません。
具体的な状況によって判断が分かれるため、弁護士などを頼りながら交渉のポイントを押さえる必要があります。
後遺障害逸失利益に関して弁護士に相談するメリット
上述のとおり、後遺障害逸失利益は複雑で難しい判断を求められるため、弁護士などの専門家にサポートしてもらうのが重要といえます。
弁護士に依頼する具体的な理由は次の3つです。
- ・適正な賠償額がわかる
- ・保険会社との交渉を任せられる
- ・増額の可能性が高まる
それぞれについて解説します。
適正な賠償額がわかる
後遺障害逸失利益は、専門的な知識がないと正しく算出するのが難しい項目です。
基準を知らないまま保険会社の提示額を受け入れてしまうと、本来もらえるべき金額より少なくなるおそれがあります。
弁護士は過去の裁判例や損害計算のルールに基づき、正しい賠償金を判断できます。
保険会社の提示している金額が適正かどうかも含め、一度弁護士に確認してもらうのがよいでしょう。
もしかしたらより高額の賠償金を請求できるかもしれません。
保険会社との交渉を任せられる
保険会社とのやり取りは、精神的にも時間的にも大きな負担です。
事故によって心身へのダメージが大きい状態のなかでの交渉となるため、想像以上の負担感があります。
また交渉の流れや内容について、どう対応していいかわからない方も少なくありません。
弁護士は依頼者の代わりに交渉を引き受け、相手の主張に適切な反論をしてくれます。
やり取りを一任できることで、被害者は治療や生活の再建にも集中しやすくなるでしょう。
交渉のプロに任せることで、有利に話をすすめることも期待できます。
増額の可能性が高まる
逸失利益を含め、提示された賠償額に納得できないケースでも、弁護士が関わることで増額が実現する事例は多くあります。
後遺障害の等級や喪失率の見直し、資料の追加などにより請求額が適正化されるためです。
保険会社は専門知識をもとに交渉をすすめてくるため、被害者が一人で対応するのは不利になりがちです。
弁護士は裁判例や交渉ノウハウを活かして主張を組み立てるため、相手側にとっても説得力が高まりますよ。
まとめ
本記事では、後遺障害逸失利益について具体的な計算方法などについて解説してきました。
ポイントは下記のとおりです。
- ・後遺障害逸失利益は、後遺障害の症状により将来得られるはずの収入が減ることによる経済的損失の賠償
- ・後遺障害逸失利益の計算式は「基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数」
- ・逸失利益額の計算は複雑かつケースバイケースなので、弁護士に相談するのがおすすめ
後遺障害逸失利益とは「見えない損失への補償」です。
「今」影響がなくても、「将来」収入に影響が出る可能性は十分あります。
交通事故後に不安を感じているなら、まずは一度、法律事務所で弁護士に話を聞いてみましょう。
初回相談は費用が無料のところもあるので、解決に向けてご活用ください。