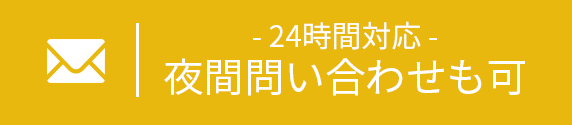コラム
交通事故で後遺障害14級に認定されるには?慰謝料や認定のポイントも弁護士が解説!
2025.11.02 慰謝料交通事故後に痛みやしびれが残り、「後遺障害14級に認定されるにはどうしたらいいの?」と悩む方は多いです。症状があっても、診断内容や書類が不十分だと認定されないこともあります。本記事では、後遺障害14級の認定基準や該当する症状、賠償金の相場(自賠責基準・弁護士基準)を弁護士が詳しく解説します。認定率を高めたい方は必見の内容です。
交通事故後、痛みやしびれが長く続いていて「後遺障害が認められないか?」と思う方は少なくありません。
症状があっても、資料や診断内容が十分でないと14級の認定が下りないことも多いのが現実です。
この記事では、後遺障害14級に認定されるための条件や流れ、賠償金の額に関する基準(自賠責基準と弁護士基準)の違いを、弁護士がわかりやすく解説します。
一読すれば、認定のポイントや必要書類の整え方、弁護士に相談するメリットが理解できるでしょう。
後遺障害14級を確実に認めてもらうには、医学的証拠の整理と専門家のサポートが欠かせません。
後遺障害14級が認められる症状は?
後遺障害14級は、後遺症の中で最も軽度な等級にあたりますが、認定率は非常に低く、正確な症状の把握と適切な資料の準備が欠かせません。
14級には1号から9号までの分類があり、症状の内容によって認定基準が異なります。
| 号数 | 主な内容 | 具体的な症状例 |
|---|---|---|
| 1号 | まぶたの欠損・まつげ脱落 | 片方のまぶたが一部欠け、白目が露出する状態 |
| 2号 | 三歯以上の欠損・補綴 | 被せ物や入れ歯で補う必要がある状態 |
| 3号 | 片耳の聴力低下 | 1m離れると小声を聞き取れない程度の難聴 |
| 4号 | 上半身の露出面に醜状痕 | 顔・腕などに手のひら大の傷跡が残る状態 |
| 5号 | 下半身の露出面に醜状痕 | 脚などに手のひら大の傷跡が残る状態 |
| 6号 | 指骨の一部欠損 | 親指以外の指骨の一部を失っている状態 |
| 7号 | 指関節の可動障害 | 親指以外の第一関節が曲げ伸ばしできない |
| 8号 | 足指の用廃 | 片足の中指から小指のうち1~2本が機能喪失 |
| 9号 | 局部に神経症状を残す | しびれ・痛み・感覚鈍麻・頭痛など |
この中でも最も多いのが「14級9号(局部に神経症状を残すもの)」です。
交通事故のむちうちや腰椎捻挫などで、治療を続けても痛みやしびれが残るケースです。
ただ、症状が一時的・断続的なものであると「常時性がない」と判断され、非該当となるケースもあります。
9号に該当するむちうち症例では、画像上で異常が見られないことも多いです。
医師の診断書や神経学的検査結果、通院履歴の一貫性が認定の決め手になります。
認定ポイントをもう少し詳しく解説します。
後遺障害14級9号を認定してもらうポイント
まず重要なのは、後遺障害診断書の自覚症状欄に「常時痛」などの具体的な症状が正確に記載されていることです。
この欄が空欄だったり曖昧な表現だったりすると、症状が軽いと判断される恐れがあります。
また、交通事故の衝撃が軽微でなかったことを示す証拠も欠かせません。
実況見分調書や修理見積書などで、衝撃の大きさを裏づける資料の提出が有効です。
さらに、治療経過の説明に矛盾がないことも重視されます。
症状が改善していないのに「良くなってきた」と伝えると、信頼性を損なう可能性があります。
正直かつ一貫した申告を心がけるべきです。
最後に、通院頻度と期間の継続性も認定の判断材料になります。
事故直後から速やかに受診し、一定期間は週1〜2回の通院を続けることが望ましいでしょう。
これらを丁寧に整えることで、認定の可能性を高められます。
後遺障害14が認定されると受け取れる賠償金額は?
交通事故で後遺障害14級が認定されると、被害者は「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を受け取れます。
金額はどの算定基準を用いるかによって大きく異なります。
主な基準は「自賠責基準」と「弁護士基準」です。
自賠責基準による賠償額
自賠責基準は、国が定める最低限の補償基準で、自動車損害賠償保障法に基づいて運用されています。
被害者が最低限の補償を受け取れるように設けられた制度で、金額は他の基準に比べて低めです。
後遺障害14級では、慰謝料32万円、逸失利益を含めた上限が75万円とされています。
手続きが簡単でスピーディーに進む反面、十分な補償とは言い難い場合もあります。
弁護士基準による賠償額
弁護士基準(裁判基準)は、実際の裁判例をもとに算定される基準です。
過去の判例を参考に、被害者が受けた精神的・経済的損失をより正確に評価します。
弁護士が介入して示談交渉を行う場合、この基準を用いるのが一般的です。
この場合、慰謝料の金額が大幅に増額される傾向があります。
後遺障害14級では慰謝料が110万円、逸失利益を含めると200万円以上になることもあります。
後遺障害14級に認定されるまでの流れとポイント
後遺障害14級に認定されるまでの手続きについては下記の流れで進めていきます。
- ・通院の継続
- ・6か月以上の通院(症状固定)
- ・後遺障害診断書を作成してもらう
- ・必要書類を自賠責保険に送る
- ・後遺障害診断書
- ・事故発生状況報告書
- ・交通事故証明書
- ・保険金支払請求書
- ・印鑑証明書
- ・検査画像など
- ・休業損害
- ・後遺障害逸失利益
- ・その他治療費等
- ・給与明細や源泉徴収票
- ・休業証明書(勤務先発行)
- ・確定申告書(自営業の場合)
- ・領収書の保管
- ・通院交通費の記録(公共交通機関・タクシー代など)
- ・付き添いが必要な場合の証明(医師の指示書)
- ・認定される可能性を高められる
- ・必要書類の作成サポートを受けられる
- ・異議申し立ても対応してもらえる
- ・後遺障害診断書の内容確認・修正指示
- ・事故証明書や医療記録の収集代行
- ・提出書類の一式管理と申請スケジュール調整
- ・14級は後遺障害の中でも最も軽度で、認定率はわずか数%
- ・神経症状や醜状痕など9号までの分類がある
- ・自賠責基準と弁護士基準では賠償額が大きく異なる
- ・通院・診断書・書類準備が認定の鍵
- ・弁護士のサポートで認定率と金額が上がる
それぞれについてポイントを含めて解説します。
通院の継続
事故後、医師の指示に従って定期的に通院を続けることが大前提です。
治療を中断すると、症状の一貫性が疑われ、軽微な障害扱いされる可能性があります。
通院を続けることで、症状の推移が医療記録として積み重なり、後遺障害認定申請時に説得力ある資料になります。
こうした通院履歴が審査で評価されるため、仕事や都合で通院を怠らないよう注意が必要です。
6か月以上の通院(症状固定)
おおよそ6か月以上通院を継続して、症状固定の判断につなげるのが実務上の目安です。
症状固定とは、「これ以上治療を行っても改善が見込めない状態」と医師が判断する段階です。
通院期間が短すぎると「治療不足」「まだまだ改善可能」と判断され、後遺症として認められにくくなります。
事故の部位や症状によっては、通院回数や間隔を医師と調整しながら継続した治療を要します。
保険会社から治療費打ち切りを告げられた際には、医師と相談して治療期間延長を検討するのも一つの対応です。
後遺障害診断書を作成してもらう
症状固定の診断を受けたら、担当医に後遺障害診断書の作成を依頼します。
この診断書には、残存する症状・治療経過・画像検査結果・自覚症状の詳細などを記載してもらう必要があるため、単に依頼するだけでは不十分です。
自覚症状(痛み・しびれの部位・頻度・重さ・日常生活への影響など)はすべて主治医に伝え、漏れなく記入してもらいましょう 。
診断書内容に不備があると、認定されないリスクが高まるため、提出前にチェックすることも大切です。
必要書類を自賠責保険に送る
後遺障害診断書が整ったら、その他必要書類と一緒に自賠責保険へ提出します。
申請方法には「被害者請求」と「事前認定」があり、被害者請求を選ぶと自ら証拠を添えて申請できて認定率を高めやすい反面、書類準備が大変です 。
主な必要書類は、
です 。
これらを揃え、期限内に自賠責保険あてに送付することで審査に入ります。
後遺障害慰謝料以外に請求できる費用
後遺障害14級が認定されると、慰謝料のほかにも請求できる費用があります。
損害を正しく補償してもらうためには、以下の3つを理解しておくことが大切です。
それぞれの内容と請求について詳しく説明します。
休業損害
交通事故によるケガで仕事を休むと、収入が減少します。
休業損害は、この減収分を補うための賠償金です。
たとえばサラリーマンであれば給与の減額分、自営業者なら営業利益の減少分が対象となります。
正確に算定するには、事故前の収入状況を示す書類が重要です。
具体的には以下のような資料です。
これらをもとに、事故によって失われた実際の収入を算定していきます。
休業損害は慰謝料とは異なり、実際の損失に基づくため、証拠書類の精度が結果を左右します。
弁護士が介入することで、保険会社との交渉を有利に進められるケースも少なくありません。
後遺障害逸失利益
上記でも説明しましたが、後遺障害が残ると将来的に働く力が低下し、減収の可能性があります。
この将来の減収を補償するのが「後遺障害逸失利益」です。
計算は「基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間」で行われ、労働能力喪失率や期間は等級ごとに異なります。
14級では労働能力喪失率5%が一般的です。
たとえば、年収500万円の方が14級認定を受けた場合、
「500万円×5%×(喪失期間に対応するライプニッツ係数)」
で算出します。
実際には職業・年齢・症状の程度によっても変動するため、弁護士が個別に計算することが望ましいです。
その他治療費等
慰謝料や休業損害以外にも、治療にかかった実費を請求できます。
治療費のほか、通院の交通費や入院時の雑費、介護・付き添い費用なども対象です。
また、ギプスやコルセット、義手などの治療用装具の購入費も含まれます。
これらの支出は一見小さく見えても、長期治療の場合は総額で大きな負担になります。
請求にあたっては、
が必要です。
実費の裏付けがあれば、適正な賠償金として認められる可能性が高まります。
後遺障害14級に認定されるには弁護士への相談がおすすめ
弁護士へ依頼する主なメリットは以下の3つです。
それぞれについて解説します。
認定される可能性を高められる
後遺障害14級は比較的軽い等級と思われがちですが、実際に認定される割合は約2〜3%と非常に低い水準にあります。
症状が残っていても、証拠や医師の診断内容が不十分だと「非該当」と判断されることが多いです。
弁護士に相談することで、医学的な証拠を適切に整理し、認定基準に沿った申請を行えます。
また、医師への説明方法や通院の記録の残し方についても助言を受けられるため、症状の一貫性を証明しやすくなります。
弁護士は被害者自身では難しい部分を補い、認定の可能性を高めることが可能です。
必要書類の作成サポートを受けられる
後遺障害の申請では、医師が作成する「後遺障害診断書」が最も重要な書類です。
ただし、一般の方が診断書の記載内容を正確に判断するのは難しく、誤記や不足があるまま提出されるケースもあります。
弁護士は、書類のチェックから修正依頼のサポートまで可能です。
などが多方面からサポートを受けられます。
これらのサポートを受けることで、申請内容の信頼性が高まり、誤りによる減額や非該当を防げます。
異議申し立ても対応してもらえる
後遺障害の申請をしても、非該当の通知を受け取るケースは珍しくありません。
その際には「異議申し立て」という再申請の手続きが認められています。
ただし、単に同じ資料を提出しても結果が覆ることはなく、不認定の原因を明確にしたうえで新たな資料の追加が必要です。
弁護士が関わると、前回の申請内容を分析し、どの点が不足していたのかを明確にしたうえで再提出できるため、再認定の可能性が高まります。
まとめ
この記事では、後遺障害14級の認定条件や該当する症状、賠償額の基準、そして申請手続きの流れについて詳しく説明しました。
記事のポイントは次のとおりです。
認定までの流れを理解したら、次に行うべきは「早めの専門家相談」です。
交通事故の被害は時間が経つほど証拠が薄れ、申請の難易度が上がります。
自分だけで抱え込まず、経験豊富な弁護士と連携して確実な結果を目指しましょう。
初回相談を無料で受け付けている法律事務所も多いため、気軽に利用するのがおすすめです。